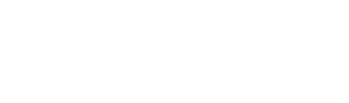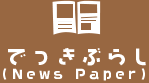31号(1983年02月)4ページ
繁殖賞を受賞した動物(第1部)
この1年間、動物園のできごと、動物のいろいろな様子を、ベスト10に組んだり、その中に苦労話やずっこけ話を織り交ぜる等して、紹介してきました。今までの“でっきぶらし”12号全部を持って園内を巡り歩けば、各々の動物の歩みが大まかながら分かり、多少なりとも親しみが湧いてくるのではないかと思います。
今回は、ちょっと視点を変えて、少し奥を見つめ、より動物を身近にさせるものがないかどうか探ってみました。出産のニュースひとつにしても、“元気に育っています。かわいいですね”だけではなく、他園ではどうなっているのか、一番最初はどこの園で産まれたのかと、疑問を持ち調べただけでも、結構面白い話題提供になりそうです。そう規模の大きくない当園でも、鳥類の繁殖を紹介した折りにふれたように、けっこう“我が国で最初に産まれた”ケースはあるのです。
そこで、当園で繁殖賞を受賞した動物を紹介しようと思います。苦労して繁殖に導き育てて得たのか、たまたま当園でしか飼育していなかったのが産まれ育って得たのか、結果は様々です。現在までに自然繁殖で9回、人工繁殖で7回受賞しています。それ等を開園時の頃より、順々に紹介してゆきましょう。
◆ダマワラビー (有袋目・カンガルー科)◆
自然:昭和44年9月10日生
昭和44年8月1日に開園して、一番最初に受賞したのが、このダマワラビーです。パルマワラビーと共に同居しており、ほぼ同じ頃にこの2種の仔がお腹の袋より顔を出して、当時の話題になっていました。困ったことに、そのころの私たちは本当に未熟で、この2種の区別が非常にあいまいでした。走る時に前足をすぼめるようにするのがパルマワラビー、八の字に広げるのがダマワラビーと覚えていても、両方が交じり合ってしまうと、とんと判らなくなってしまったのです。
今から思うと、よく見れば体の大きさも違うし体毛の色の違う、どうしてあんなに違う種が区別できなかったのか、不思議に思えてなりません。
こんなに区別のつかなかったことが気に病まれるのは、当時、パルマワラビーも繁殖賞の候補だったからです。早めに申請したダマワラビーは獲得できたものの、一方のパルマワラビーはそんな状況でしたから、多摩動物公園に先を越されてしまいました。もっとも、これはお互い様だったようで、多摩のほうは多摩のほうで、やはりダマワラビーも繁殖しており、一足遅れの申請に悔しがったとか、悔しがらなかったとかの話しを聞きました。
で、そのダマワラビーは、どこで飼育しているのかと聞かれても困ります。この良種は非常に交配し易く、雑種が次々にできてしまう為、そんなまずさを取除こうと、かれこれ8〜9年前になるでしょうか、その時点で、メスの多かったパルマワラビーを残し、ダマワラビーは放出することになりました。
と言う訳で、現在はもう飼育されておりません。せっかく繁殖賞を受賞したものをどうしてと思われるかもしれませんが、雑種を平気で増やしているようでは、動物園の良識が疑われます。その辺のところを理解して頂きたいと思います。
◆ハイイロキツネザル (霊長目・キツネザル科)◆
自然:昭和49年4月25日生
どこの動物園でも飼育されていた訳ではなかったことから、繁殖させれば当然繁殖賞と言うことになります。こんな風に切り出せば、たいしたことないようですが、もしこれから飼育する機会が得られる園館があるとしても、そう簡単に繁殖させることはできないでしょう。
通常、八百屋から購入している餌だけに頼らないで、担当者は山の中に入って、彼らの好みそうな自然の餌を求めました。春先には竹の子の皮のやわらかい部分、女竹の竹の子を与えたり、更にシーズンを通して彼らの好みの竹の葉を与え続ける等、餌ひとつにしても、これだけの工夫を凝らしていたのです。習性をつかむのも大変なことでした。いくら参考書があり、それを調べたからと言っても、限度があります。“他園の飼育例がない”は、繁殖賞を得るのにチャンスではあったものの、この方法が正しいと言い切れず、ずいぶん模索を続けました。
そんな苦労を続けて、今までに繁殖したのは後に人工哺育で繁殖賞を取った例も含めて、わずかに3頭だけです。最近では、発情がきたと言う話しすら聞けなくなりました。
◆アメリカオシ (ガンカモ目・ガンカモ科)◆
人工:昭和49年4月28日生
自然:昭和49年5月15日生
フライングゲージで飼育されているサギ類やガンカモ類、その他いくつかの鳥類、この中の何種類が繁殖したかは、鳥類の繁殖(10号)を参照して貰えれば分かります。その中で、繁殖賞(自然、人工両方)を獲得しているのがアメリカオシです。別段自慢するほどのことではなく、他園であまり飼育しておらず、たまたま一番乗りしたと言うのが事実のようです。
このアメリカオシは、繁殖賞を獲得した年だけにとどまらず、その後の数年間に渡って、いくつものペアが次から次へと、ヒナをかえしてくれました。一度に5〜6羽なんてのはざら、多い時には9羽もかえしたのですから、何とも旺盛な繁殖力でした。全部が全部育った訳ではありませんが、実に、総数100羽以上繁殖し、育った数も80羽以上に及びました。鳥類の繁殖の折りにもふれたように、当園でこれだけフ化し育った例は他にはありません。
今、思い出しても、彼らが顔を出す春先が、フライングゲージのもっとも生き生きしていた時期だったでしょうか。春のうららに任せて、母親が池でスイスイ泳ぎ、その後をピィピィとヒナがついて行く、仕事をしていてもつい手を止められる愛らしい風情です。担当者もそんな春を迎えたくて、冬の間一生懸命巣箱を作ったり、巣箱の置き場所を探したり、巣材を運んだりしたのでしょうか。
そう思うと、ここ何年かアメリカオシの繁殖の声が聞かれないのは、残念な気がしてきます。
◆ダイアナモンキー (霊長目・オナガザル科)◆
人工:昭和49年7月29日生
当時はもうダイアナモンキーの出産なんておかしくも珍しくもありませんでした。が、人工哺育の例がないなんて意外、ヘェーと驚いたものです。“でっきぶらし”読者なら、ここで“ぐうたらママワースト10”を思い出して頂けるかと思います。そう、確かに汚名を返上していたものの、前科4犯で第5位にランクされていました。
ジミーと命名された、この仔を産んだ時の扱いのひどかったこと、一言では言い表せません。逆さに抱くは、水につけるは、ひきずるは、置きざりにこそしなかったものの、このままでは殺される、そんなひっ迫した感じを受けたものでした。どうやって取り上げたのか、記憶にはありません。扱いのひどさが強烈で、そればかりが印象に残ってしまっているのです。
忙しい担当者に代って、快く面倒を見てくれた代番者、彼の手によってジミーは育てられました。すでに歯が生えかかっていて、思いの他丈夫さを感じさせましたが、何と言っても、たったの365グラム、人の赤ちゃんの10分の1ぐらいしかありません。下手に下痢させたり、カゼをひかせると大変、アッと言う間にあの世へ行かせてしまいます。
何とか大過なく育ち、散歩に連れて貰える頃になったジミーは、ちょこまか動くひょうきんさに、すっかり飼育係の人気者になっていました。が、困ったのはその後の扱いです。親との同居を試みても、メス親は受け入れてくれたものの、オス親の強烈な洗礼に合い、手、足、尾を咬まれて失敗、同居を諦めざるを得ませんでした。
親との同居を断念、それはジミーにとって、この動物園とのお別れを意味しました。結局、他園で欲しているところがあると言うことで、動物商に引き取られて行きました。
◆ハイイロキツネザル (霊長目・キツネザル科)◆
人工:昭和50年7月13日生
前回の出産より1年余り後、2度目の出産でした。全てが予定通りに進行、1度うまく育てた個体が、その次の出産でへまをやらかす、そんなことは、まず常識では考えられません。確かに、見た眼には前回と何ら変わりなく、母親のふところに、うずくまるように抱かれています。しかし、担当者の眼には、根拠がないものの、不吉な予感がよぎっていました。何か、どこかがおかしい。“カン”としか言いようがないものの、そう感じていたのです。
翌日には、誰の眼にも疑いなく、衰弱している様子がうかがえました。急いで取り上げた仔の体重はわずかに39グラム。こんな小さな仔を育てるのは、とても無理と思え、1度は親に戻すことを考えました。しかし、乳首に吸いつく力もない仔を親に戻しても、死を待つだけです。むざむざ死をを待つぐらいならと、担当者の持てる力を全てぶつけての挑戦が始まりました。育てる自信はどうであれ、何もしないで死を待つ程、飼育係にとって悔しい、悲しいことはありません。やれるだけやってみるだけです。
ミルクを飲ませると言っても、1回の哺乳量は、わずかに1〜2cc。それを、3時間置きぐらいに与えようと言うのですから、どれぐらい根気を必要としたか、言葉に絶します。哺乳量は少しずつのびはしても、その間にカゼはひく、便秘はする、元気になったと思ったら、茶柵に飛びついて落っこち怪我をする、とまあこんな苦労を続けながらよくもあんな小さな仔が無事に育ったものと、今考えても不思議なくらいです。
実際、繁殖賞の一覧表を見て、俗に、ポケットモンキーと言われるマーモセット類の自然繁殖は、いくらかあるのですが、人工繁殖は全く見当たりません。如何に大変な人工哺育であったのか分かって貰えると思います。そう言う意味では、ハイイロキツネザルの人工哺育における繁殖賞は、素晴らしい賞と言えます。
◆アカガシラエボシドリ (ホトトギス目・エボシドリ科)◆
自然:昭和50年8月25日生
繁殖の過程については、鳥類の繁殖(10号)で述べました。ここでは重複するので、それは省かせて頂きます。
どこの動物園でも熱帯の鳥類を飼育するとなれば、必ずエボシドリを含めると思います。それほど色あざやかで美しく、いかにも熱帯の鳥と思わせる雰囲気を漂わせているからです。事実、当園においても、このアカガシラエボシドリの他に、オウカンエボシドリを飼育し、過去のムラサキエボシドリやニシズキンエボシドリを含めると、4種類飼育したことになります。
えてしてそんな鳥類程、飼育がむつかしいものです。あでやかな色彩を維持するのに四苦八苦の状態で、とても繁殖どころではないのが実情でしょう。一番古い繁殖例が、京都動物園の昭和49年5月5日にフ化したエボシドリ(別種)です。当園のアカガシラエボシドリがフ化するわずか1年3ヶ月前のこと。その後はと調べても、やはり京都動物園のオウカンエボシドリ、56年5月17日フ化の例があるだけです。むずかしい、むずかしいを連発し安売りしているようですが、エボシドリの繁殖賞獲得は、わずかに3例しかないのです。決して大げさでないのが、分かって貰えると思います。当園でも、よくヒナを育てたメスが死んだ後は、ピタリと繁殖は止まってしまっているのです。
4月に完成予定の熱帯鳥類館、ここでまたエボシドリを始め、様々な鳥類が飼育されるでしょう。もしエボシドリが繁殖すれば、例えそれが2度目、3度目であっても、やはりビッグニュースとして取り上げられます。
◆キンカジュー (食肉目・アライグマ科)◆
人工:昭和50年9月15日生
キンカジューの自然繁殖による繁殖賞は、これより10年前に、京都動物園がすでに受けていました。“人工哺育例がない”には、ダイアナモンキー同様いささか驚きました。繁殖賞一覧表を見ても、自然繁殖例があって、人工繁殖例がないケースは、割合にあるものです。それは無理に人工哺育までして、わざわざ繁殖賞を狙ったりしないからだと思います。
当園の場合も、正にやむを得ぬ理由からでした。夕方に生まれて、そのまま様子を見ていると、面倒をみるどころか、左耳をかじり出したのです。これには慌て、急いで人工哺育に切り換えました。
キンカジューでメスだからキンコ、そう名付けられ、当時まだ新米だった女性獣医の手に委ねられました。夕方の散歩時間、キィーキィー鳴きながら、養母の後を必死について行く、そんなキンコの姿が、ふと浮かび上がってきます。人工哺育にして何がかわいいと言えば、こうして顔を覚えて非常になついてくれる時です。
しかし、もう1度やりたいかと聞いても、やりたいと答える飼育係はまずいないでしょう。大変だからやりたくないのではありません。人工哺育にしてしまうと、自分と同じ仲間と上手に付き合えない動物になってしまうからです。しかも、逆境に耐えられないと言うか、何とも言いようのない弱さを内包した個体にしてしまいます。そんな風に動物を育てあげても、全く空しいばかりです。
キンコも結局親元に返すことができず、動物商の手に渡りました。飼いきれなければ、やむを得ないことです。ただせつなく思うのは、キンコはその環境の変化に耐えられなかったことです。拒食を起こし、最後まで何も食べずに死んでいったと言う報に、何ともやりきれない寂しさだけが残りました。自然繁殖の個体だったら、あんなことにはならなかった、そんな気がしてなりません。
次号に続く、お楽しみに!
(松下憲行)