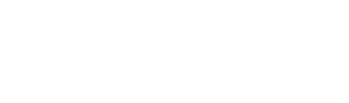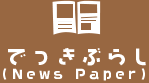46号(1985年08月)6ページ
良母愚母 第7回 ◎小型サル(愚母はコモンマーモセットだけ)
俗にポケットモンキーといわれるキヌザルの仲間です。日本平動物園では割合多くの種類が飼育され、繁殖もけっこう多く見られました。その数は6種類に及びますが、一度にその種名を挙げるとイメージとして捕え辛いでしょうか。身体のある部分の特長を捕えて種名がついていますから、そこから、繁殖した小型サルのそれぞれのイメージを作り上げて頂ければいかがでしょう。
尾が黒ければオグロマーモセット。綿の帽子をかぶっているようであればワタボウシパンシェ。顔から首筋にかけて毛がうんと黒ければクロクビタマリン。手が赤ければアカテタマリン。胸が赤ければムネアカタマリン。と言う風にです。コモンは平凡という意味。コモンマーモセットはそれだけ平凡で数が多い小型のサル、と思って貰えれば良いでしょう。
さて本題に戻って、それぞれのお母さんぶり。オグロマーモセットの最後の繁殖は、もう6年ぐらい前になるのではないでしょうか。私がカメラをいじくり出し、繁殖した動物に目を向け始めたばかりの頃でした。5〜6頭いながらメスは1頭だけ、そんな不自然な形の中で―。
この小型サルの、面白いというか不思議というか変わった習性は、父親が子守りをすることです。授乳をする時だけ母親、それが終わると又父親がやって来て、さっさとおんぶして連れていってしまいます。ですから、カメラを構えて母子で撮っているつもりが、実は父子であったことが多々ありました。もっともそのほうが自然な形の親子の写真であったでしょう。
そんな変わった習性が、オスがいっぱいいる中でもさしてトラブルもなく、出産を促したのかもしれません。他のサル類ではこうはいきません。特にマカクやヒヒ類では、オス同士の凄惨なトラブルを招くだけで、繁殖どころではなくなってしまいます。それに子守りをするしゃれた習性も、当然のことながら持ち合わせてはいません。
そのメスも子を産んでから、1年も満たないうちに死んでしまいました。子はすでに離乳しており、他のオスにもすっかり馴染んでいて、後々の成長には差しつかえなかったものの、繁殖の夢はその段階で消え去りました。今はもう、アルバムを見て当時を偲ぶだけです。
私が、夢中になってカメラを振り回していた頃、最も多くの子育てを見せてくれたのが、ワタボウシパンシェとクロクビタマリンです。さながら、それは競演でした。どちらが育てるのが上手か、そしてたくさん産むかです。が、それを何度か繰り返す内、両方ともに狭いところでひしめき合うようになりました。
こうなると、繁殖はストップします。あるいは、産まれても事故死や病死するケースが続発します。クロクビタマリンとワタボウシパンシェ、悪いほうのそのケースまで競演してくれました。
これらの繁殖の話題が途切れた頃に、コモンマーモセットが出産!の報。それではいっちょう張り切って写真でも撮るかと、コモンマーモセットの放飼場を見渡しましたが、肝腎の子がいません。ん?なんと床に落ちているのです。これには驚きました。急いで担当者に報せたものの、放棄された子の運命は哀れです。翌日か翌々日に衰弱死してしまいました。
翌年の春にも、又出産。当然、人工哺育です。床に子を捨ててしまう母親に任せる訳にはいきません。でも、赤ん坊の体重はわずかに23g。技術うんぬんより、神だのみです。赤ん坊の生命力に賭けるしかなかったでしょう。
のぞみと名付けられた赤ちゃんは、無事に育てられました。その過程には、担当する者しかわからない苦労が多々あったと思います。ミルクを飲ませるにも、最初は1回に1cc飲んでくれればいい方なのですから―。
日本で最初の人工哺育で育てられた個体であるのぞみ。可愛がられた割には薄幸な運命を歩みました。病弱で、特に何かの事故で尾の骨を折ってからは、体調はより思わしくなくなっていったようです。私自身、最後にのぞみを見たのは、病院で保育器に入れられて息も絶え絶えになっている姿でした。
ムネアカタマリンには、流産のイメージがついて回ります。「涙を飲んだ動物たち・その後」の中でも、その経過を簡単に述べました。そして新しくやって来たメスに希望を託すと締め括ったその後は―。
そう、ムネアカタマリンもいいメスに巡り合いさえすれば、の典型でした。繁殖はどちらかと言わずとも他力本願です。飼育係がしゃかりきになって頑張ろうとも、悪い個体に巡り合ってしまえばどうしようもありません。逆にいい個体に巡り合えば、多少いい加減に扱っても、繁殖は割合にスムースにゆくものです。
飼育係にとって必要なのは、いい個体に巡り合った場合の環境作りでしょう。交尾から妊娠、出産にかけて細やかに配慮、育児期には母子に対してより一層の栄養のバランスを考え、そしてどんな小さな変化をも逃さずに記録してゆくことだと思います。
その意味では、アカテタマリンは教訓的でした。無事出産させながら、育児過程で子を死に追いやってしまったのですから―。
担当者が言うには、離乳からしばらくすると、やたら動物性たん白質を欲するようになったので、懸命に与えたが、その時はすでに遅かったそうです。私もかつてシロガオオマキザルの飼育で、大失敗をやらかしました。それは、アカテタマリンの比ではありません。彼等が、恒常的に多くの動物性たん白質を欲し、必要としているのを見抜けず、幾度となく流産、死産を繰り返させてしまったのです。
他人があれこれ言わなくとも、そんな失敗で一番悔しい思いをするのは担当者です。何処が、何が、何故、いけなかったのか真剣に悩み思い込んで次に向かいます。
2度目に産まれたアカテタマリンの子は、今元気に育っています。この子が無事に成長した時、前回と比べて何処をどのように変え、工夫したのか、自らの飼育技術をみがく為にも、ぜひ知り教わらなければならないでしょう。