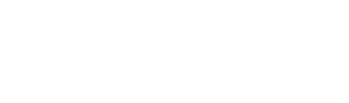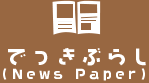62号(1988年03月)5ページ
動物病院てんやわんや〜人工哺育抄〜◎コモンマーモセットの出産
これぐらいだったら「まあまあとにかく頑張ろう」で済みます。しかしながら、これらはまだ第1章、第2章の始まりにしか過ぎなかったのです。
ヒョウ、ツチブタの生まれた翌日、今度はコモンマーモセットが出産しました。かつて2度に渡って妊娠するも出産できずに親子もろともの悲劇を繰り返した後に迎えた、まだ2〜3才の若い個体の出産でした。当然、どう面倒を見るかは心配です。1頭は死産で床に落ちていましたが、もう1頭は当園生まれの父親が一応おんぶしていました。一応?夫婦、時には家族で面倒を見るのは、マーモセットやタマリンの習性です。父親がおんぶしているのは、微笑ましくも至極当たり前のこと。少々気に掛かったのは、その位置が肩のところではなく腰の辺りで、しかも母親に渡す様子が全く見られなかったことです。担当する私自身、それは不安でした。
そして翌日、心配でたまらなくなって早出してきた獣医と私の目の前で、子は親にしがみつく力を失って台の上で横たえました。落下しなかったのは不幸中の幸い。落ちていれば脳内出血であっさりあの世行きだったでしょう。いきさつをもう一度詳しく述べるなら、朝一番に見た時は、母親につくにはついていました。しかしそれはなんと尻尾の付け根、とても哺乳できる位置ではありませんでした。なおかつ子にはい上がる力もないようでした。「これは危ない。取ろう。」とは、獣医、担当の私どちらからともなく出た言葉でした。親から子が離れたのは、正にその直後だったのです。
子は冷えきっており、もう2〜30分取り上げるのが遅ければ死んでいたかもしれません。とにかく獣医も私も必死。何とか生かしたい、それだけでした。ところで女性の乳房がこんなにも素晴らしいものかと、私は改めて感心、感激しました。何たって、25gの小さな赤ん坊の下がった体温を上げ、見事に甦らせたのです。命の源でなくて何でありましょう。
これが第3章。決して終わりではありません。まだ続くのです。私の頭の中には、4月の半ばには生まれるであろうピグミーマーモセットのことが頭から離れなかったし、他の飼育係はキリンやチンパンジーのことが頭から離れなかったでしょう。
とにかく、そういう心構えを胸に秘めて各動物の担当者と代番者が集合、人工哺育のチーム作りが行なわれました。つまり私はコモンマーモセットにミルクを与える傍らツチブタの哺乳の手伝い、逆にツチブタの担当者はコモンマーモセットの哺乳を手伝うという風にです。獣医はもっと大変。総合的に助力、助言しなければならなかったのですから―。