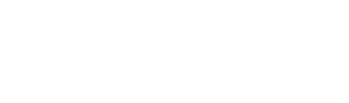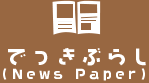78号(1990年11月)1ページ
一九九〇年を振り返って
年末の慌しさが増すある日の昼過ぎ、日誌をめくる獣医の顔色がどうも冴えません。いえ、悔恨を胸に秘めた表情ですらありました。
ツチブタが二度目の出産をしたことは何度かお伝えしていますが、問題はその過程です。人工哺育はやむを得ないとして、育て方に大きな過ちを犯してしまったのではなかろうか、と疑問を抱き始めていたのです。
哺乳も離乳もうまくゆき過ぎる程うまくゆきました。前回の苦労など全くウソのようでした。えてして、そんな時程落とし穴があるものです。
足の動きに異変を感じたのは、三ヶ月近く経った十一月の初め頃だったでしょうか。で、レントゲンを撮ってびっくり!!白くはっきり写る筈の骨が薄くにしか浮かび上がってこなかったのです。
離乳が早過ぎたのでは、夜行性館に移すのが早過ぎたのでは、と骨折以前の問題に獣医の胸はチクチク痛みます。これは、むしろ私達飼育係が気をつけねばならず、引いては押し寄せる波のように繰り返す悩み、苦しみです。
★ニューフェイスは…
ニューフェイスの少ない年でした。そんな中でひときわ異彩を放ったのが、ゲルディモンキー。でも、取材に来られた若い新聞記者は、何をポイントにしていいか分からないと、嘆いたこと、嘆いたこと。
見た目には、全身が黒くて体重が五〜六百gの小さいサルです。どこがどう変わっている訳でもありません。絵にならない、記事にならない点では満点に近く、記者の嘆かれた気持ちはよく分かりました。
しかしながら私達、特に私にとっては全身が震える程の魅力を与えてくれたサルでした。
こんなに面白くて可愛い奴と毎日顔を合わせられると、心は躍っていました。
ちょっとむつかしい話をするなら、南アメリカに棲むサルは、マーモセット類とオマキザル類とに大別されます。そして、このゲルディモンキーというのがその中間的存在になるのです。つまり、マーモセットの特窒ニオマキザルの特窒?合わせ持っているのです。
それを目の当たりにできる、飼育することによって中間的存在の意味をしっかり勉強できる、飼育係冥利につきます。
シシオザルも数少ないニューフェイスのひとつです。かつてはありふれたサルで、どこの動物園ででもごくふつうに見られました。それが、今では稀少動物です。
平たくいってしまえばニホンザルやアカゲザルと同じマカクの仲間で、飼育そのものもさしてむつかしくはなく、様相がライオン(獅子)に似ているだけに、面白いといえば面白い程度です。
ただここで感心するのは、彼らの落ち着きぶりです。常識的には環境が変わるのは、非常に強いストレスです。時には命さえ奪いかねません。
それがこのシシオザルといい、ゲルティモンキーといい、昨年のエンペラータマリンといい、ビクともしない強さというか動じないおおらかさを持ち合わせています。
スイス、カナダ、イギリス、それぞれの出所の国名です。何か飼育方法が違い、それを学ぶ為に実習に行けるものなら行きたいぐらいです。
この他にカピバラ、アカハシハジロ、オマキトカゲなどが、新たにお目見えしています。
★賑やか家族を形成したのは…
ブラッザグェノンが今年も出産の報に。早速カメラを持って向かいました。どれがいつ生まれたのか分からないぐらい。放飼場のあちこちに大きいのやら小さいのやらが散らばっています。
すっかり長くのびてしまった母親の乳首をしっかりくわえて離さない子のそばに、一匹やんちゃ坊主がいます。一年経ってもう構ってもらえない寂しさからか、はたまた何かせずにはいられない旺盛な好奇心からか、とにかく悪戯をして回っています。
その内オス親の背中にドーン、無視されると更に強くドーン、怒ったオス親が咬みつきかからんばかりの表情になると、すたこらさっさと逃げてしまいます。しつけが悪いといわんばかりに、このオス親は母親に八つ当たりです。びっくり仰天のこの母親、平身低頭してただただ平謝りです。
八月末日の午後のこの光景、母親がちょっぴりかわいそうでおかしくもありますが、繁殖の大元を仕掛けた私にとっては感慨深くもあります。かれこれ十年前、ぎくしゃくしていたこのオスとメスの仲を取り持った記憶が懐かしく甦ります。
世界でいちばん小さなサルであることが売り物のピグミーマーモセット。写真で見ると面白くても実際にはあまり目立たない存在でした。それも、何年か前までの話。一年に二度、しかもたいていは二頭で生まれる繁殖力は、たちまちの内に賑やかな家族になってゆきました。
今年も四月十六日に二頭、十一月十七日にも一頭が生まれ、いずれも元気に育っています。合計九頭、これだけいれば少々小さくたってけっこう目立つものです。
「わあっ小ちゃいね」「ねっねっあそこにもいるよ。ここにもいるよ。あれえー。あんな小っこいのもいる」「ホントだ。可愛いいー。」春から秋にかけて、子供達が多い時にはよくこんな会話が聞かれました。
サルにしても草食獣にしても、一度に生まれるのは一頭が常識的で、二頭で生まれるのはやや例外です。が、鳥、ことにカモ類になると逆、一度に十羽近くかえることもそう珍しいことではありません。
フライングケージ内で威張り散らしていたカナダガンが池に放り出された後、やや勢力を持ち出してきたのがツクシガモ。で、我が世の春という訳でもないでしょうが、六月四日にかえったひなの数はなんと九羽で、一気に賑やかな家族です。
野生では天敵が多くて、半数も無事に育たないでしょう。かの有名なカルガモの親子も、人に近づくのはカラスやネズミなどの天敵を避ける為では、といわれています。
ツクシガモにしたってフライングケージの中、恐いカラスの襲撃もなければ、ネズミがひなをパクッもありません。ゆうゆう自適の親子暮らしです。気をつけねばならないのは病気、それだけでした。
母親がひなを懐にかばっているのを見ているとまるで袴をはいているようとは、獣医や担当者の話。ある時、正にそのとおりの光景に出会いました。
カメラを向けると私を気にしてか、一羽、又一羽と池に入り母親の後を追ってゆきます。再び池から上がった母親が立ち止まると、次から次へとひなが母親の懐へ入り込んでゆきます。徐々に足元はふくらみ、遂に懐は袴のような形になってしまいました。
途中、病気で二羽死んでしまいましたが、残りの七羽は無事に育ちました。八十%近い成育率は、何と言っても飼育下のなせる業です。
この他、オグロワラビーやバーバリシープがより賑やかな家族を形成、爬虫類館ではケニアスナボアが一気に十五頭も出産する出来事もありました。一九九〇年の繁殖は、哺乳類、鳥類、爬虫類を合わせ、計三十一種類でした。
★死出の旅路についた者達は…
生きる努力、人工哺育されている動物を見ていると、しばしばその気概があるのかとの思いにかられます。しっかり飲まない、食べない、動かない、依頼心ばかりが強い、などなど…。
今回のオグロワラビーは、正にその典型でした。担当者にそれを補助した獣医、我慢強さでは誰にもひけを取らないのは自他共に認めるところです。
その二人が幾度となく苛立ちの表情を見せました。午後一時のミーティングに来なかったことも度々ありました。昼過ぎに始めた哺乳が終わらなかった為です。
時間だけを見ればけっこう飲んでいるようですが、その実わずか十cc、二十ccを飲んでくれなくてうんうん苦しんでいたのです。何と生きる努力をしないオグロワラビーでしょう。
固形食をほどほど食べるようになると、哺乳は打ち切られました。わずかしか飲まないのなら、あえて与える必要もないだろうと判断したのでした。
それでもけっこう調子はよさそうでした。が、ある日突然体調を崩したかと思うと、そのままダウン。二度と起き上がることはありませんでした。
わずか十cc、二十ccでも、ワラビーの子にはまだ必要だったのかもしれません。生きる努力をしなかったのだから致し方ないといってしまえばそれまでですが、やはり悔いは残るでしょう。
ミルク、それにタマゴは、サルを飼育するにあたって欠かせない食物である。私はそう信じて疑っていません。事実、それらをよく摂取しているサルは毛づやもよく体格もがっちりしています。
では、それで万全!?つい最近まではそこまでゆかなくとも九割方の安全保障を得たものと考えていました。でも、今は違います。やや迷路に入り込んでいます。
人工哺育の空しさはともかく、ピグミーマーモセットとコモンマーモセットの経験を通じて、おおむね栄養障害は出さない術を身につけたつもりでいました。
しかながら、ムネアカタマリンにはそれが通じませんでした。ミルクをよく飲み、離乳も順調、体が大きい分だけ量もしっかり取っていたのにも拘らずです。
何かおかしいと感じながら、リリィーと名付けた彼女を見つめていました。歩きはしても決して飛び跳ねようとはしないのです。よく見ると脚が悪く、特に左側がほっそりしていました。
そして誕生日を迎えた頃、九月下旬、ほんのわずか気温が下がっただけでガタガタ震えて寒がりました。室温は夏場に比べて下がったとはいえ、最低でも二十三〜四度ありました。それでも体力のない彼女にしてみれば、寒くて寒くてたまらなかったのです。
急いで入院させ、保育器に入れたものの、その日の内にあえなく昇天。死因は肺炎ですが、育て方に問題があったことは一目瞭然でした。
悔いるより、悩みが深くなるばかりです。この他にも、二度の出産の後に体調を崩して死んだクロミミマーモセット、丁度十八頭生んだ後に死んだアカテタマリン、両方とも骨が変形していました。カルシウムの補強が足りなかったといわれても致し方ありません。
新たに迎えた動物を飼育しかつ生と死を見つめて得た自身と生涯引きずってゆくであろう悔恨。どちらが大きいかと問われてなくとも後者。この他の出来事とも相まって、様々な想いを残し一九九〇年は去ってゆきました。